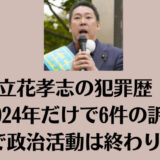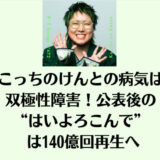日産とホンダの経営統合に関する協議は以前から進められてきましたが、ついに合併します。
「日産とホンダがなぜ協業?」「メリットは何か」「将来性はあるのか」が気になります。
本記事では、合併の主なメリットとその背景を分かりやすくご紹介します。
(2025年2月18日追記)二社の経営統合の話は一度破談しましたが、協議の再開の可能性が浮上しています。
それでは早速見てみましょう!
日産とホンダはなぜ合併?3大メリットで生き残りをかけた経営戦略
日産とホンダはなぜ合併を計画したのでしょうか。
そこには世界市場で生き残るための経営戦略がありました。
大きく分けた3つのメリットをご紹介します。
合併のメリット①EV開発に向けたコスト削減とリソースの共有
まず1つ目の日産とホンダの合併のメリットは、EV開発に向けたコスト削減とリソースの共有ができることです。
両社が経営統合することにより、開発コストを分担することができます。
現在は、世界市場において特に電気自動車(EV)の開発が期待されていますが、
日産は、今後3年間で発売予定の新型車30車種のうち、16車種を電動車とし、EVの割合を20%に増加させる計画です。(23年度は9%)(参照:読売新聞)
ホンダは、2040年までに新車販売をすべてEVと燃料電池車(FCV)に切り替えることを目標にすると2021年に発表していました。(参照:日経XTECH)
両社が協業することにより、個々の企業が負担する投資リスクを軽減し、より迅速な製品展開が可能になります。
合併のメリット②技術力の結集が可能に
2つ目の日産とホンダの合併のメリットは、技術力の結集です。
ホンダは、高性能エンジン技術や二輪車事業に強みを持つことは周知の事実でしょう。
2023年度の二輪事業の営業利益は過去最高を更新し、販売台数は前年度比0.3%増加。(参照:honda)
世界市場の販売台数ではホンダが1位で、二輪・バイクのトップシェアは断トツです。(参照:PROVE)
日産は、電動化技術において独自の技術を有しています。
2010年に世界で初めて量産型の電気自動車(EV)「日産リーフ」を発売し、そこから今日に至るまでEV技術を磨いてきました。
特筆すべきは、日産独自の電動パワートレイン「e-POWER」を開発です。
「日産リーフ」のバッテリーや制御の技術を応用し製造されたもので、その走りは高く評価されています。(参照:PRtimes)
これらの両社の強みを組み合わせることで、グローバル市場での競争力を強化し、シェア拡大を目指すことができます。
合併のメリット③世界市場での競争力の向上
3つ目の日産とホンダの合併のメリットは、世界市場での競争力の向上です。
日産とホンダの合併によって、日産が筆頭株主の三菱自動車を加えた新たな企業グループとなり、年間800万台の販売を見込むことができます。
となると、トヨタやフォルクスワーゲンに次ぐ、世界第3位の自動車メーカーということになります。
規模の拡大により、世界市場での競争力を高めることが可能となります。

なぜ合弁に至ったのか:背景と必要性
そもそもなぜ日産とホンダは合弁に至る必要性があったのでしょうか。その背景に迫りましょう。
EVや自動運転技術の開発が急務に
現在自動車業界では、アメリカのテスラや中国のBYDなどの新興企業(*)が先行している中で、EVや自動運転技術の開発が急務となっています。
日系企業はこの競争に遅れを取っているため、統合による協力が必要とされています。
(*)テスラ、BYD共に自動車産業への参入は2003年
経営がひっ迫状況にあった
日産とホンダが合弁に至る必要があったのは、両社ともに経営上の課題を抱えており、ひっ迫状況にあったからです。
特に日産は最近の中間決算で利益が大幅に減少していました。
2024年9月半期の中間決算では、営業利益が前年同期比90.2%減、純利益が93.5%減だったことが発表されています。(参照:朝日新聞)
このような状況下での経営統合は、生き残りをかけた戦略として位置づけられます。
日産は欧州以外で協業先を探していた
また日産は、先にフランス大手ルノーとの協業の他、欧州以外で協業先を探していました。
日産は仏自動車大手ルノーと資本関係の対等化が完了し、欧州以外で協業先を探していた。(2024/03/15 引用:産経新聞)
ホンダは車の電動化・知能化が課題だった
ホンダは、車の電動化・知能化が課題でした。
〝独立志向〟を貫いていたホンダも車の電動化や知能化を自前化するのが難しくなっており、日産との協業検討を後押しした。(2024/03/15 引用:産経新聞)
ホンダと日産の経営統合は破談に
(2025年2月5日現在)経営統合の話は破談になりました。
当初は、ホンダと日産で持ち株会社を作り、それぞれを傘下とする形での経営統合を目指していたはすですが、その後、日産をホンダの子会社とする案が出されていました。
子会社化を断固反対する日産が、協議を打ち切る方針を固めたといいます。(参照:newsdig)
協議でぶつかった問題①リストラ
ホンダと日産の経営統合の協議を進める中で出てきた問題1つめは、リストラの問題です。
経営統合にあたり、日産のリストラの実現が前提条件でしたが、時間が経ってもなかなか進められませんでした。
協議でぶつかった問題②技術力
ホンダと日産の経営統合の協議を進める中で出てきた問題2つめは、技術力の問題です。
日産独自のハイブリット技術である「e-POWER」が、ホンダ独自のハイブリット車に劣らないと言われた点です。
実際に、日産の「e-POWER」は国土が広いアメリカで走るには燃費が悪く、投入できていませんが、ホンダのハイブリット車は高速走行時の燃費が良く、北米で販売が伸びています。
日産の主力技術に対しても否定される事態となれば、決裂は免れない状況です。
協議の再開?!
2025年2月18日、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じたところによると、
ホンダの関係者が
「日産自動車の内田誠社長が退き、日産社内の反対をよりうまく制御できる新トップが就任すれば、日産との協議を再開する用意がある。」
と明かしたと報じました。(参照:bloomberg)
統合に向けた協議の再開の可能性が再浮上しています。
日産の内田誠社長が退任【決定】
2025年2月27日、Bloombergによると、日産自動車は内田誠社長兼最高経営責任者(CEO)を退任させることを視野に調整を始めたと報道しました。
これには、ホンダとの統合協議が頓挫したこともその要因の一つだと言われています。(参照:Bloomberg)
(2025年3月11日追記)取締役会にて内田誠社長が3月末を以て退任することが決定しました。
日産の新社長は誰になる?
日産自動車の新社長は誰になるのでしょうか。
ダイヤモンド編集部の調べによると、後任はジェレミー・パパンCFO(最高財務責任者)となる予定だと言われています。(参照:diamond)
(2025年3月11日追記)予想とは異なり、商品企画を統括してきたイヴァン・エスピノーサ氏(46)が後任となる人事が発表されました。
新社長が就任した暁には、ホンダとの統合交渉を再開する見通しも立てられているかもしれません。
引き続き、動向を見守ります。
まとめ
日産とホンダの合併によって、コスト削減や技術力の結集、世界市場での競争力の向上を目指す上で重要な戦略であり、急速に変化する自動車業界において生き残るための必要なステップといえるでしょう。
経営統合には、企業文化や経営戦略の違いなど克服する必要性がでてくる可能性はありますが、それらを乗り越えることで、より強固な企業体制を築くことができると期待されています。